♯036 藤原綾乃さん
公益財団法人 福武財団
直島、豊島、犬島を舞台に展開している「ベネッセアートサイト直島」。公益財団法人 福武財団の藤原さんは、昨今話題になっている対話型鑑賞など、アートを活用した教育企画を子どもから大人まで幅広く届けています。「大人になっても変わるきっかけをつくれるのなら、やるしかない。」と話す藤原さんのお仕事についてお伺いしました。(聞き手:森分志学)

誰にも負けない意気込みが対話型鑑賞に行き着く
森分:まず、大学に進むまでの経緯を教えてください。
藤原:生まれも育ちもずっと岡山です。両親が医療系なので、最初は医療系に進むものだと思って育ちました。でも小学校の文集を見ると、「楽しいものを作り出す仕事がしたい」って書いてあって、「おお、いいこと言ってるな」と思ったんです。とはいえ中学生くらいからは、「医療系に行くんだ」って思い込んで勉強を頑張ってました。ただ成績も医学部を目指すほどでもなく、生物より物理が好きで医療系の仕事にあまり興味がなかったんです。
それで、仲が良かった美術の先生から「建築に行ったら?」って言われて、理系でアートっぽい要素があるなら面白いんじゃないかと思い、「建築行こうかな」って思ったのがきっかけです。
森分:新卒で福武財団に入られたそうですが、なぜ福武財団だったんですか?
藤原:東京の大学を出て、最初は大学院にも行って東京で仕事をしたいと思ってたんですけど、せわしない街がちょっと自分に合わなくて、岡山に帰ろうと思いました。ただ、同級生は都会で働いてる人が多かったので、岡山でも負けない仕事ができそうな場所と考えて直島を選びました。
森分:岡山で負けない仕事ができそうな場所、ですか。
藤原:東京ではできない仕事がここにはあると思ったんです。ほかに同じようなことをしてるところもなくて、都会の人たちもわざわざ来るぐらい評価されている場所です。私も直島や犬島がアートプロジェクトになる前からよく遊びに行ってたんです。
森分:入社当時の直島ってどんな様子だったんですか?
藤原:ちょうど李禹煥(リ ウファン)美術館がオープンする年で、私はそこの初期メンバーに配属されました。そのときに第1回目の瀬戸内国際芸術祭が始まったので、職員や拠点を増やす時期だったんです。
森分:対話型鑑賞はどのような経緯で導入されたのでしょう?
藤原:李禹煥美術館の運営が軌道に乗ったら、ツアー商品を作ろうという話になりました。地中美術館には有料のプライベートツアーがあったので、李禹煥美術館も個人のお客さん向けのツアーを作ることになったんです。ただ、作品がシンプルなので、説明だけで魅力を伝えるのは難しかったんです。オープンしてしばらく様子を見ていたら、「よく分かりませんでした」と言って5分くらいで帰ってしまうお客さんも多く、「どう見たらいいか教えてほしい」とよく言われたんですが、ただ解説するだけでは限界がありますし、そもそも私たちの理念は「よく生きる」を体験してもらうこと。そのためには、説明じゃなくてお客さんの主観を引き出す方法が合うんじゃないかと、メンバーと試行錯誤している中で対話型鑑賞にたどり着きました。最初は社内でも理解されにくかったですが、だんだん定着してきているんじゃないかと思います。
様々な教育企画をつくる
森分:対話型鑑賞以外にも印象的だった企画ってありますか?
藤原:小学生向けの「冒険ブック」というツールを開発したり、14歳限定のアートフェスを企画したりしました。一昨年は富士通さんとコラボして、聴覚障害の方が使う「Ontenna」(オンテナ)というデバイスを使った豊島での鑑賞ワークショップをやりましたが、それはすごく印象に残ってます。
森分:どんなワークショップだったんですか?
藤原:富士通が開発した「Ontenna」って、音を振動と光に変換する小さなデバイスなんですけど、開発者の本多さんとお話する機会があり、それを借りていろんな美術館で試したら、豊島にある心臓音のアーカイブで手に持っていた時に、手の中に心臓があるみたいで面白いなと思ったんです。。本多さんと「じゃあ豊島で何かやりましょう」となって、香川県の聾学校と豊島中学校に声をかけて、企画したんです。
豊島の中学生15人、聾学校の子たち12人が参加してくれて、豊島の子は手話を覚えて紙芝居で紹介してくれたり、お互いに豊島美術館や心臓音のアーカイブを一緒に見て、Ontennaがあるとき・ないときでどう違うか、作品鑑賞を通じてどんなことを考えたかを書き合ったんです。障がいの有る無しを超えて、一人ひとりが違っていることや、言葉を話せなくてもコミュニケーションができることを子どもたちが体得していたのが感動的でした。この取り組みは、文化庁メディア芸術祭の審査委員会推薦作品に選ばれました。
森分:面白いですね。14歳のアートフェスについても教えてください。
藤原:対話型鑑賞で非認知能力にどう変容するかをベネッセと一緒に研究している中で思いついた企画です。その研究の一環として、オンラインで対話型鑑賞の授業を何回もやったんです。そのとき感じたのは、中学生って自己理解へのモチベーションが高いんだなということです。「自分は何者なのか」「何が得意で、何がやりたいのか」を知りたがる子が多くて。アート鑑賞をすると自分の個性がわかるし、ほかの人の感じ方を知ることで、自分の強みに気づく子もたくさんいました。今まで短所だと思っていたことが実は長所だったとか、思ったことをなんでも話せて受け入れてもらえるのが嬉しかったとか、日常生活でも些細なものに目が留まるようになったとか、人の立場に立って考えられるようになったとか、うれしいコメントが多かったです。
14歳って悩みも多い時期ですし、中学生の自殺が多いという話もあって、少しでも自分を知るきっかけをつくれたら、健やかに過ごせるんじゃないかなと思ったんです。それで「アート鑑賞を通じて自分を知ろう、自分の未来について考えよう」という14歳限定のイベントをやろうと思ったのがきっかけです。
森分:今回で何回目ですか?
藤原:まだ2回目です。初回に参加したある生徒は普段自分の意見を言わない、引っ込み思案なタイプだったんですが、ちゃんと好きな作品を選んで未来のテーマを考え、最後は発表までしてくれました。「中学生って本当にいろいろ考えてるんだな」と思いました。生きることや死ぬことなど、普段あまり表に出さないような深いことを考え始める時期なんですね。そういう気持ちを安心して吐き出せる場って大事だと思うし、普段は同級生や親に見せる自分をある程度作っている部分もあると思うので、まったく初めて会う子たち同士なら外からの目を気にせず自分を出せるんじゃないかなと思いました。
森分:色々とされてますが、藤原さんの守備範囲ってどこまでなんでしょう?
藤原:私はできるだけ守備範囲を広げたいんです。「よく生きる」をアートを通じて考えることはどんな分野でも親和性が高いと思っています。たとえばテクノロジー系の「Ontenna」みたいなものもウェルカムだし、何でも投げ込んでほしいですね。
森分:どんな人に届けたいですか?
藤原:学校プログラムでは高校生がメインターゲットですが、私個人としては「よく生きる」ことに興味がある人なら属性は問いません。
森分:「よく生きる」というのはゴール地点として意識しているんですか?
藤原:そうですね。「よく生きる」というのは財団の理念でもあるので、私自身も大事にしています。

藤原さんのよく生きるとは、無色透明になること
森分:「よく生きる」って何だと思いますか?
藤原:その人が自分の「よく生きる」とは何かが言えるようになることが一つのゴールかなと思います。もちろん答えは一つじゃなくて、人によっては家族との会話を増やすことだったり、自分を大事にすることだったりするかもしれないし、同じ人でも時が違えば変わるかもしれません。
まずは自分の状態を知るところから始まると思うんです。今の自分のコンディションや潜在意識を知って、「もっとこうなりたいけど、今はここにいるんだな」と気づいたりすることがスタート地点かなと。そこにまだ立てていない人が多いので、まずは自分の状態をしっかり認識してもらう。それがあまりよくない状況だったとしても、受容できる。少なくとも「よし、やってみよう」と思えるところまでは寄り添いたいですね。
森分:藤原さんにとっての「よく生きる」って何でしょう?
藤原:うーん、難しいですね。私は無色透明になることが目標で、対話型鑑賞でも、いずれはファシリテーターがいなくても自然と対話が生まれて、みんなが自分で気づいたり考えたりできる状態がゴールかなと思っています。だから、最終的には私がいなくなることがゴールかなと思います。
森分:文化になるということですね。
藤原:名誉理事長の福武總一郎は「アートがインフラになる」と言いますが、まさに当たり前になる感じです。直島の子どもたちはアートが日常にあるので、好奇心や積極性が自然に育つんですよね。そんなふうに、存在自体はあまり意識されていないのに、実は源になっているものがアート、みたいな。
アートがインフラになるとは何か
森分:アートがインフラになるとは、アートのどんな機能を指してるんでしょう。
藤原:作家の見ている世界を、作品というメガネを通して覗かせてもらえるところが大きいと思います。私たちには気づかない視点を、アーティストは作品で提示してくれる。そこから「こんな見方もあるのかも」って発想が広がるんですよね。アーティストって普段の生活では気づかない視点をもっているからアーティストになってると思うんですけど、その世界をのぞくことで新しい発想や、自分の関心事とのつながりが生まれやすいかなと。
森分:ちょっと作家の人格を借りる、みたいな感じなんですかね。
藤原:そんな感じかもしれませんね。何もないよりは作品というきかっけがあったほうが自分の思考や潜在意識・関心が引き出されやすいと思います。
森分: それがアートのインフラ化とどうつながるんでしょう。
藤原:アートがインフラになるっていうのは、アートが日常に溶け込んで不可欠なものになるということなので、身の回りにアートを感じいろんな見方や自分の主観を常に認識して表現しようとすることが日常的になる、ということかなと思います。もしかしたらアートの概念も広がって、コップ1個でできちゃうのがゴールかもしれませんけどね。
森分:確かに作品を目の前にすると、「なんでこんなの作ったんだろう?」って思うところから入りますよね。
藤原:そうなんです。作品がなかったら、自分が赤色好きだって気づかなかった、みたいなこともあるかもしれないんですよ。「教育とは変わることだ」と言っている人がいて、すごくいい言葉だと思ったんです。大人は自分は変わらないって思いがちだけど、対話型鑑賞をやると驚くほど変わる人がいる。こんなに変われるツールってなかなかないんじゃないかっていうのが私の実感で、それがモチベーションにもなっています。大人も変われるきっかけが作れるなら、やるしかないだろうっていう使命感ですね。
森分:そこにもエンジンがあるんですね。
藤原:ええ。私自身のモチベーションは、やっぱり人がどう変わるかを見たいっていうところが大きいです。

自分の主観に価値があると気づけるか
森分:自分のテーマを見つける過程においてアートが最適だということですが、アートにどういう可能性を感じていますか?
藤原:アートの個人的な解釈には優劣がないと思っています。特に現代アートは、作品をどう見るか、何を感じるかは鑑賞者それぞれで、作家の意図やメッセージもあると思うんですが、個人が感じたことには上下や正誤はないんじゃないかと。だからこそ、ありのままの自分を受け止めやすい。その点がすごく大きいと思います。だから例えばネガティブな印象を持っても大丈夫というか、包容力があるんです。
森分:主観を引き出すのにアートが最適ということですね。
藤原:そう思います。何と結びつけるかは自由ですし、作品を見てゲームや食べ物、おばあちゃんとの思い出を話す人もいれば、急に数学の話になる人もいる。そういう幅の広さがいいんですよね。
森分:藤原さんが「これいい瞬間だな」と思うのはどんなときですか?
藤原:まず言葉がうまく出なかった人が「私はこう思う」と言い始めたときは、すごくうれしいです。逆に考えるのが好きで言語化に慣れている人は最初から普通にしゃべり始めるので、「面白いですね」って肯定するだけなんですが、その人に「じゃあ外側はどうなってるんでしょうね?」と聞いてみたとき、「ああ、そうか」と新しい発見があったりする瞬間があるんです。考えるポテンシャルはあったけど、そこまで行かなかった領域まで踏み込めたような感じがする。
あと、人は頭では「みんな違うことを考えている」とわかっていても、体感としてそれを落とし込めていない場合があるんです。実感したときに「本当に人って違うんですね」と改めて言う人がいるんですが、そこがスイッチが入った瞬間だなと思います。
森分:なるほど。これまでの話が藤原さんの中ではつながっているんですね。
藤原:はい。自分の主観に価値があると気づくかどうかが重要だと思います。気づいていないと、「よく生きる」が他人から押し付けられたものになったり、自分の中ではなく外側に答えを探してしまう可能性がありますよね。自分が考えたことや、やりたいことに「これが自分の正解だ」と言えるかどうか。その土台こそが対話型鑑賞にあると思うんです。そこを押さえれば、「今はこれに興味があるからやりたいんだ」と思ったときに、自分のミッションとしてちゃんと捉えられるようになる。「こう思ったからこれが私の正解です」と自信をもって言えるようになる。そのための基礎やマインドを作るのが対話型鑑賞の役割じゃないかなと思っています。
森分:藤原さんの中で自己と社会の概念はどのような関係性ですか?
藤原:自分の強みを理解していないと、それを社会で活かせないんじゃないかと思います。ビジネスパーソンとして仕事をこなすだけならAIで代替できる部分もありますよね。でも個性や強みがあるからこそ、仕事にいろんなアイディアが生まれて、新しいものを生み出せると思うんです。そうやって社会も良くなっていくはずで、そのためには自己理解を深めて、自分がやりたいことに全力を注げる人を増やしたいという思いがあります。そうすれば社会で生き生きと活躍する人が増えたり、仕事も面白くなるんじゃないかと、、最終的にはそこにつながる気がします。

自分の主観をちゃんと言葉にできるように
森分:自分の主観を言葉にしづらい人に対して、どうサポートされているんでしょうか。
藤原:1回の対話型鑑賞が30分や1時間だと、すぐに変化を起こすのは難しいので、2日間などしっかりプログラムを組みます。最初は全然話せなくても、次は少し言葉にしてみよう、という流れを作ります。
「どこが気になったんだろう?」と気づくのを手伝う感じです。「今、どの辺見てました?」とか「この色が気になった?」と聞いてみる。最初は単語しか返ってこなくても、質問を繰り返すうちに「何でその色が気になったのか」とか「そこから何を連想したのか」を自然に考えるようになるんです。はじめは戸惑って答えられなくても、後半になると「私はここに注目しました。なぜなら…」と自分から言えるようになる人もいて、それがすごくうれしいですね。
森分:だんだん補助輪が外れていくイメージですね。その変化って本人も実感してるんですか。
藤原:結構うれしそうにしています。自分では気づいてない人もいて、「そんなに変わってますか?」と聞かれることもありますが、「いや、めちゃくちゃ変わってますよ」って(笑)。
森分:具体的なエピソードはありますか。
藤原:研修で直島に来た方で、アートに全然興味がない方がいました。2日間で3回くらい対話型鑑賞をやって、1か月後に振り返り研修をしたんですね。そしたら「家族旅行で行く先を考えるとき、美術館があるか調べるようになったんです」っておっしゃって。「人生の中でアート鑑賞をほとんどしたことがなかったのに、直島での経験をきっかけに変わりました」と言っていただいて、私もうれしかったです。
森分:何が変化のきっかけだったんでしょうか?
藤原:いちばん印象に残ったのは、私が「すごく変わったよ」とフィードバックしたことだったみたいです。本人はあまり意識してなかったみたいなんですけど、「自分の主観をちゃんと言葉にできるようになってますよ」って伝えたら、それがすごく印象的だったようで、もっと続けてみたいと思われたのかなと思います。
アート×Xで新しい何かを生み出す
森分:藤原さんがこれからやりたいことや野望があれば教えてください。
藤原:最近一級建築士を取ったので、それも生かさないといけないなとは思っています。私は飽きっぽくて、新しいことをやり続けないと退屈するので、「ここは絶対結びつかないだろう」というものをかけ合わせたり、プログラムを常に進化させたいと思っています。
森分:藤原さんご自身は、どんな役割がしっくりきていますか?
藤原:私は「1を10にする」より「0から1を作る」ほうが楽しいタイプですね。市場のないところに市場を作るとか。アートによる教育という分野もまだ大きな市場ではないと思うので、そこに可能性を感じています。美術教育の中にしかアートがないという状況より、非認知能力や探究学習など、科目じゃないところにアートが入るといいなと思うんです。
森分:「アート×X」という感じなんですね。
藤原:今いる環境での武器がアートなので、自然と「アート×何か」になります。建築をやっていたからか、同時に色んなアイデアを行き来させるのは好きです。一つのことに集中するより、色々やっているほうがいい相乗効果が生まれると思っています。
森分:クリエイター的でもありますね。
藤原:私、本当は人前で話すとか接客とかが一番苦手で、最初は裏方に回りたかったんです。でも7年くらい現場でお客様対応をしているうちに慣れたというか、いま一番苦手なはずの仕事をやっているんですよね。だから何が起こるかわからないなと思います。
森分:ありがとうございます。
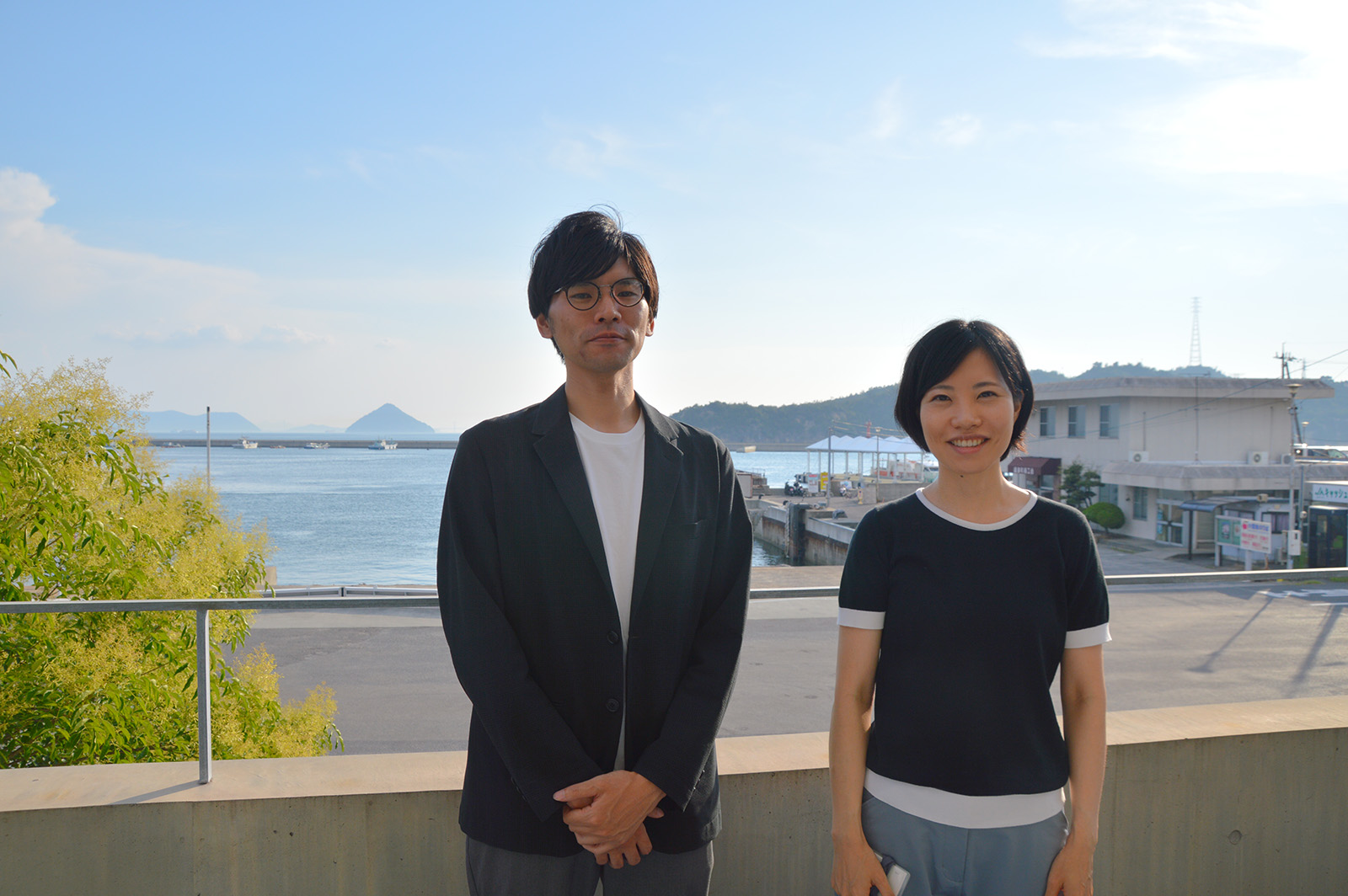
(取材日:2023/07/28)

